「どこの裁判所で破産手続き(裁判)を行うか」についてのルールのことを「管轄」といいます。
日本の裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所があり、また、下級裁判所は、同種の裁判所が多数存在しています。そして、ある裁判をこれら多種多数の裁判所のうちの、いずれの裁判所が担当するかについての定めのことを「管轄」というわけです。
例えば、AさんがB会社を経営していて、AさんとB会社が破産する場合で、同時に(Aさんの奥さんである)Cさんも(住宅ローンの連帯保証債務が払えず)破産する場合。
| 住民票の住所(所有自宅) | さいたま地方裁判所 川越支部 |
|---|---|
| 実際に住んでいる住所(単身赴任) | さいたま地方裁判所 熊谷支部 |
| 登記がある住所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 実際の事務所の住所 | 横浜地方裁判所 |
| 住民票の住所(所有自宅) | さいたま地方裁判所 川越支部 |
|---|---|
| 実際に住んでいる住所 | さいたま地方裁判所 川越支部 |
上のような場合、
と4つの管轄がありますが、通常はどの裁判所でも(Aさん・B会社・Cさん[2人+1社]を一緒に)破産申立が可能です。
※ タキオン法律事務所では、最も迅速かつ管財人予納金が明確な「東京地方裁判所」で破産申立を行うことが多いです。詳細は「東京地裁での会社の自己破産手続き申立のメリットは?」を参照してください。
ここでは、「職分管轄」「土地管轄」「専属管轄」の3つの法定管轄につき説明します。かなり専門的ですので飛ばしていただいても大丈夫です。
破産事件は地方裁判所の管轄に属する(破産法5条)。
土地管轄は、次のとおり様々な特則が設けられています (破5条)。
債務者が営業者である場合は、主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が管轄する(破5条1項前段)。 「主たる営業所」とは、会社法上の定款所定の本店の意味です。
なお、登記簿上の本店と現実の本店営業所が一致しない場合は、東京地方裁判所では、いずれでも可能とされています。
自然人の場合は、住居所などです。
親法人が子会社である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する関係にある場合、一方の親法人又は子会社について破産事件、再生事件が係属しているときは、 他方の親法人又は子会社の破産手続開始の申立ては、 他方の親法人又は子会社の破産事件等が係属している裁判所にもすることができる(破5条3項)。
法人とその代表者について、一方に破産事件等が係属しているときは、 他方の法人又はその代表者の破産手続開始の申立ては、法人又はその代表者の破産事件等が既に係属している裁判所にもすることができる(破5条6項)。
相互に連帯債務者の関係にある個人、 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人及び夫婦のうち、 一方について破産事件が係属しているときは、他方の破産手続開始の申立ては当該破産事件が係属している裁判所にもすることができる (破5条7項)。
破産債権者となるべき債権者の数が500人以上の破産事件の場合、原 則的及び補充的土地管轄による裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する他の裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる (破5条8項)。 また、破産債権者となるべき債権者の数1,000人以上の破産事件の場合は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる(破5条9項)。
破産事件の管轄は、専属管轄である(破6条)。合意管轄や応訴管轄は認められない。管轄違いと認めるときは管轄裁判所に移送しなければならない(破13条)。
(破産事件の管轄)
第四条 この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。第五条 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 前項の規定による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3 前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第八十三条第二項第二号及び第三項並びに第百六十一条第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては、親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては、子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
4 子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては、当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
6 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
7 第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
一 相互に連帯債務者の関係にある個人
二 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
三 夫婦
8 第一項及び第二項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
9 第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項に規定する債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
10 前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。(専属管轄)
第六条 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。(破産事件の移送)
破産法
第七条 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三 第五条第二項に規定する地方裁判所
四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ 第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハ ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
五 第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
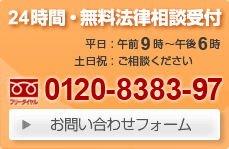
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
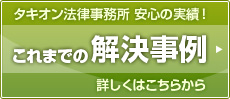

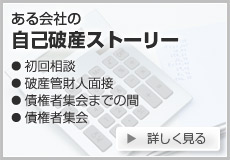




タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
 三田線 内幸町駅 徒歩3分
三田線 内幸町駅 徒歩3分
 銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
 JR線 新橋駅 徒歩6分
JR線 新橋駅 徒歩6分
 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
 千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
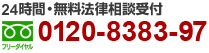
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
営業時間(平日の夜・土日祝対応)
全日:午前9時~午後9時
※弁護士と事務員が在席していなくても電話代行サービスにつながります。その場合は氏名・住所・連絡先(例:タナカタロウ・東京都・携帯***-****-****)を伝えて頂ければ、できるだけ早いうちに弁護士から折り返しの電話を差し上げるようにしております。